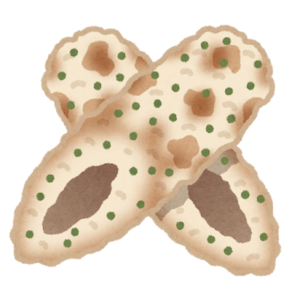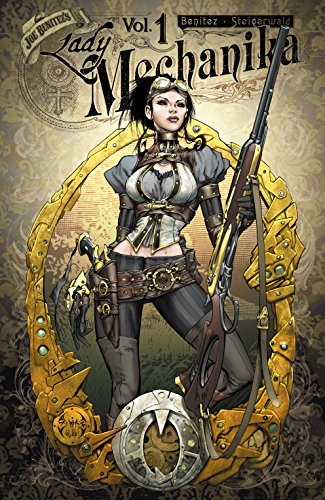話は1967年に始まる。日本ではグループサウンズがブームとなり、第2次佐藤内閣が発足し、高度経済成長期の真っ只中であるが、中国では、50年代の大躍進政策で失敗し国家主席を辞任していた毛沢東の権力奪還の手段として始まった文化大革命が、そのピークを迎えていた。
話は1967年に始まる。日本ではグループサウンズがブームとなり、第2次佐藤内閣が発足し、高度経済成長期の真っ只中であるが、中国では、50年代の大躍進政策で失敗し国家主席を辞任していた毛沢東の権力奪還の手段として始まった文化大革命が、そのピークを迎えていた。
主要人物のひとり葉文潔の父親は理論物理学者で、反動的学術権威として紅衛兵たちに吊し上げられる。文潔の妹は過激な紅衛兵となって積極的に父親の罪を暴いていたのであり、同じ物理学者の母親はとうに自己批判しており、批判集会で夫を反革命分子として非難する。しかし、頑なに自己批判を拒んだ父親は、4人の少女たちにベルトで殴られて死亡する。その光景を目の当たりにしていた文潔は人類に深く絶望する。
――人類に絶望? そうなの? それは「人類」なの?
いやいや、それを突き詰めてはいけない。そして、天安門事件についてはまったく触れられていない(ただ、作中はっきり明記はされていないのだが、経過年数を数えていくと1989年に”あること”が起きる)。
2000年代の亡命中国作家たちは文革については語りにくいようなことを言っていたが、今はそれほどでもないのだろうか。六四天安門事件は依然としてタブーらしいが、それは禁じられているというだけではなくて、中国人に語る必要がなくなってしまったということもあるのではないかという気が最近している。
1986年に胡耀邦が百花斉放・百家争鳴と言ってから中国でもマルクス以外の西洋哲学の「批判的」受容ということがあったようで、ニューアカブームの余熱冷めやらぬ日本の大学で、僕はホワイトヘッドとかフォイエルバッハといった名が中国語で書かれている論文を読まされたりしていた。それで中国の民主化というと、僕はどうしても「大学でホワイトヘッドなんかの研究をしている人がいる」ってことだと考えてしまう。だから、天安門のニュースを見たときに頭に浮かんだのは、文革よろしくホワイトヘッドの研究者が三角帽子を被せられて首から「私は懷海德を読みました」という板っきれを提げて小突かれている姿だった。
つまり、日本人の僕でさえそんなイメージを思い浮かべたのだから、『三体』の冒頭というのは文革の実態というよりもそのステロタイプでしかないとも考えられるのだが、まあ、それはそれとして、あの89年にそのまま中国が民主化していたらどうなのよ、という疑問がこないだからずっと気になっているところなのだ。
僕らはあのとき中国の民主化を「たぶん」歓迎していた。でも、それって阿呆らしい優越感の反映だったかもしれない。僕らは彼らを「無知で貧しい10億の民」だと考え、下に見ていたのではないか。資本主義陣営に入ってきた彼らを馬鹿にしてあごで使うつもりだったのではないか。少なくとも当時の高度資本主義国家のわが国が東南アジア諸国とどういう関係を築いていたかを思い出せば、あながちこの想像が的外れでもないことは同意してもらえるんじゃないかと思う。
この日本とアジアの国の関係については、84年の「吉本埴谷コムデギャルソン論争」も僕は気にかかるのだ。この笑ってしまうような論争は、あの「an an」に吉本隆明がコムデギャルソンの服を着せられて載ったことに対して、埴谷雄高が「それを見たらタイの青年は悪魔と思うだろう」とイチャモンをつけて始まった論争だが、このときの吉本の反論は「先進資本主義国日本の中級ないし下級の女子賃労働者は、こんなファッション便覧に眼くばりするような消費生活をもてるほど、豊かになった」のだというものだった。もちろん、日本の賃労働者が「豊かになった」前提には「タイ」の賃労働者の労働があり、その賃金は日本の労働者と比較して相対的に低い。この同時的差異に立脚していたのが埴谷だとすれば、吉本はかつての「日本」の労働者の状況に「タイ」の労働者が到達したのだという通時的運動を見ていたのだと思う。
この「タイ」のところに「中国」も入れていたというのが当時の日本であり世界だ。それは民主化の如何を問わない。あれから30年経って、さて現在あの国に暮らしているのは「賢くて金持ちの13億人」である。GDPはとっくのとうに日本を抜いて世界2位。民主化しなかったのにこの「ありさま」だ。
民主化していたらいったいどうなっていたのだろう? 変わっていただろうか。変わっていたとすればどう変わっていたのだ? 現在のタイやフィリピンと同じ立ち位置であると想像してみよう。現在の中国の人たちはそれを良しとするだろうか。
間違いないのは、この30年で中国人が絶対的不可逆的に「幸福」になったということだ。中級ないし下級の女子賃労働者がファッション便覧に眼くばりするような消費生活をもてるほど豊かになったという事実だ。日本人が「天安門」なんて口にしなくても生きていけるのと同様、中国人も「天安門」をネットで検索する必要なんてないのだ。言い換えればそれは「歴史」になってしまったのだ。(ああ、ようやく『三体』に戻ってこられた。読んだ人にはわかるよね?)。
だから、天安門を問題にしたり、2019年香港民主化デモを考えるとき、僕らは何を守ろう/獲得しようとしているのかを、あらためて自らに問い直すべきなのだ。それは「自由」なのか。その「自由」とはどんなものなのか。「公共」と「自由」の線引きをどこでするのか。それは自分が決めることなのか。それとも誰かが決めることなのか(「自由」なのに?)。
有限な個人はより長期的に存在する社会に優先しうるか。時間の長さが問題なら、普遍なる神には従うべきではないのか。個が無力であるときは集合体でしか語れないのか。
『三体』の終わりに蝗が登場するのと『高い城の男』の『イナゴ身重く横たわる』には何の関連もないのだろうが、ふと読み返してみたくなって本棚を探しても見当たらない。段ボールに入れてしまってしまったらしい。段ボールの山をひっくり返すのもアレなので、思わずkindle本で購入してしまった僕なのだ。


 話は1967年に始まる。日本ではグループサウンズがブームとなり、第2次佐藤内閣が発足し、高度経済成長期の真っ只中であるが、中国では、50年代の大躍進政策で失敗し国家主席を辞任していた毛沢東の権力奪還の手段として始まった文化大革命が、そのピークを迎えていた。
話は1967年に始まる。日本ではグループサウンズがブームとなり、第2次佐藤内閣が発足し、高度経済成長期の真っ只中であるが、中国では、50年代の大躍進政策で失敗し国家主席を辞任していた毛沢東の権力奪還の手段として始まった文化大革命が、そのピークを迎えていた。 どうしてそうなったのか委細は知らないが、「木島日記」は「北神伝綺」の、あるいは折口信夫-木島平八郎の組み合わせは柳田国男-兵頭北神の組み合わせの「もどき」であったはずだ。
どうしてそうなったのか委細は知らないが、「木島日記」は「北神伝綺」の、あるいは折口信夫-木島平八郎の組み合わせは柳田国男-兵頭北神の組み合わせの「もどき」であったはずだ。